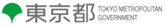サポート紹介&利用者の声

SUPPORT 2025.11.17
~未来に希望を持ってともに成長して~
一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会(CAN)
家族のケアをしている人たちが集い、思いを打ち明けたり、情報を得たりするピアサポートの場を提供しています。
高校生のきょうだい児と大人のきょうだいがまったく同じ思いを抱えていることに気づき、いままでケアラーがケアされてこなかったことに驚くこともありました。
きょうだいやケアラーと積極的に出会って希望の光をつないでいってほしいです。それができる場がここ(CAN)です。
一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会(CAN) 代表理事 持田恭子さん
ケアラーアクションネットワーク協会(CAN)とは?
ケアラーアクションネットワーク協会(CAN)は、10代から60代までの幅広いケアラーをサポートし、交流の場を提供している団体です。「ケアラー同士が出逢い、語り合い、共に成長しあいながら、希望溢れる社会を創造すること」を理念に掲げて活動しています。
家族のケアをしている人たちが集い、思いを打ち明けたり、情報を得たりするピアサポートの場を提供しています。交流はオンラインおよびリアルで実施しています。
また、ピアメンター育成や、ヤングケアラーを含むケアラーの理解を深めるための啓発や広報活動にも注力しています。
自身の体験をもとにケアラーが交流する場を提供する団体に

私は小学生の頃から、両親の感情面のサポートとダウン症候群がある兄の生活面のケアをしてきたので、今でいうヤングケアラーでした。自分と似た境遇の方に会いたくて1996年にホームページを開設し、仲間を募って「きょうだい同士のオンライン交流会」を始めました。当時は主に仕事が終わった後にメールでやりとりをして、80人近い方々とのつながりができました。
一時期、母の在宅介護と兄のケアに加え、仕事や家事など様々なことが重なって、活動を休止した期間がありました。その間、きょうだい同士のコミュニケーションを休止したわけですが、職場では家族介護やケアラーとしての話題を、周りの人に共感してもらうことがとても難しいということに気づいたんですね。
この経験から、家族目線でケアの課題を考え、主体的に解決する必要があると強く思い、団体として活動をスタートしました。最初は一人の参加者から始まった活動が、30人以上の方々が集う場へと成長しました。
コロナ禍になって、対面で集まって活動することが難しくなったので中高生向けにオンラインでの交流を始めました。全国どこからでも参加できるので好評です。
現在は、大人のきょうだいやケアラーを対象とした対面の集いも再開し、通算100回目を突破して持続的に活動しています。
ケアラー同士の交流を後押しする活動

主な交流会として、学生など25歳以下の方を対象に主にオンラインで実施している「ほっと一息タイム」と、幅広い年代を対象に対面で実施している「きょうだい&ケアラーの集い」の二つのイベントがあります。
交流会では、自身の体験を似たような境遇の方と共有しあったり複数人でグループワークをしたりします。高校生が対面の交流会に参加することもあります。
また、行政機関からのヒアリングにお答えすることもあるのですが、高校生のきょうだい児と大人のきょうだいがまったく同じ思いを抱えていることに気づき、いままでケアラーがケアされてこなかったことに驚くこともありました。
ケアラーは、自分や家族だけでケアを抱えがちで、孤独を感じたり、周囲から孤立してしまうことがあります。ですから交流会は、誰にも言えずに抱えていた家族のことや学校・職場での出来事、あるいは進学・就職についての悩みや個人的な関心事について話して、共感し合ったり、一緒に考えたりする貴重な場になっています。
ケアラー自身の感情のケアに注力
団体の活動では特に、ケアラーの感情のケアに力を入れています。悩みを打ち明け合ったり、話し合ったりすることはベースにありますが、それだけだと毎回同じ話をすることになるので、テーマを決めて、感じたことや思ったことを言葉にしてみんなで考えるようにしています。
たとえば、ひとりが「いらいらした」と話したとすると、その裏にはどんな感情があったのだろうか、本当は相手にどうしてもらいたかったのか、ということを言葉に出して、みんなで話し合って深掘りしていきます。そうすると、「実は話を聞いてもらいたかった」というように、感情の裏にあった願いや気持ちに気づくことができるんです。
「自己投影視点」で想像してくれる人を増やしたい

ケアラーの悩みとしてよく聞くのは、「家族のことを身近な人に気軽に打ち明けにくい」ということです。家族をケアしていることを話して「大変だね」と言われて会話が終わってしまったり、話題を変えられたりすると、それ以上話せなくなってしまうことがあります。
そんなときは、「それでどうしたの?」と関心を持ってもらえたら話を続けるきっかけになるんですよね。
家族をケアすることは、誰にでも起こりうることです。人によって感じ方が多様にあるので、どんな気持ちもあっていい、とお互いを尊重できる社会の形成を目指しています。
他にも、わたしたちが制作した映画の上映や講演をしています。小中学校では出前授業を実施して、相手の立場に自分を置き換えて「もし自分が家族のケアをしていたらどう感じるか、どうするだろうか」「周りの人に何をしてもらいたいか」と想像して意見交換をする人権教育を行っています。
SNSで個別相談ができる「ほっと一息LINE」
大人数で集まって話すことが苦手な方やハードルが高いと感じている方のために「ほっと一息LINE」という個別相談も行っています。作業療法士、障害者施設支援員、キャリアコンサルタントといった相談員が、LINEチャットで様々な相談に対応しています。
個別相談の対応時間は平日の18~22時ですが、受付は24時間です。家族をケアしている若者だけでなく、親御さんや支援者など幅広い方々からの相談があります。具体的な相談だけでなく、漠然とした不安やちょっと愚痴を聞いて欲しいといったことも相談することができます。
交流会に参加して、個別に話したいことがあるので「ほっと一息LINE」も活用する、といった使い方もできます。
啓発に注力、映画制作も
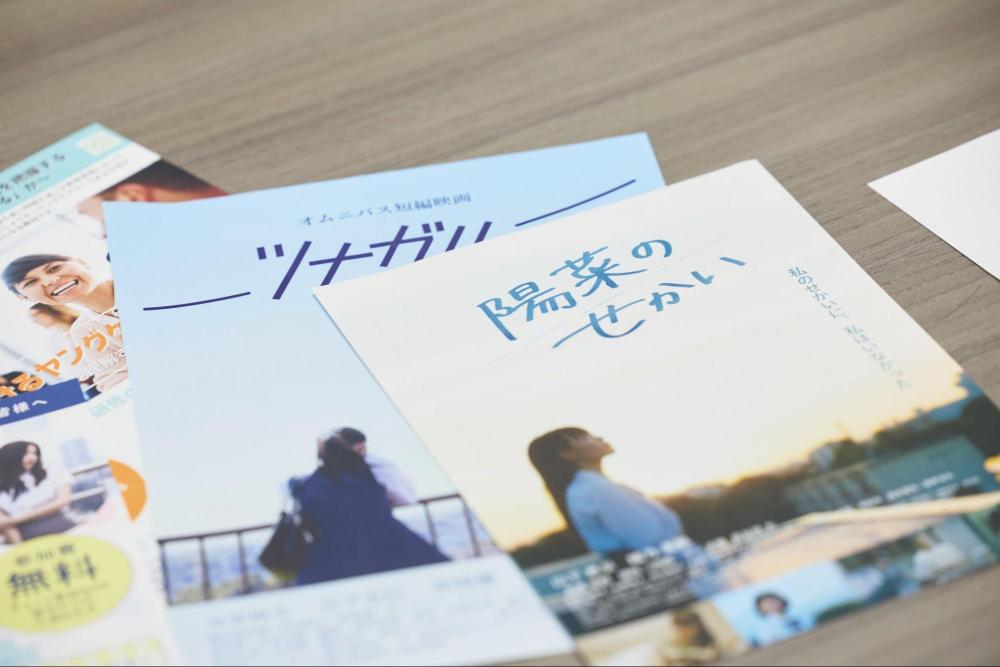
ヤングケアラーを含むケアラーについて、より多くの方に知ってもらうため、映画も制作しました。1作目の「陽菜(ひな)のせかい」は、高校時代の私の体験と現代の高校生の実体験を混ぜ合わせた短編作品で、2021年に制作しました。進路に悩む高校生の葛藤を描いた作品で、大手動画配信サービスでも視聴することができるので、ぜひ検索してみて下さい。
2作目の「ツナガル」は2024年に制作した作品です。「ほっと一息タイム」に参加していた高校生や大学生が自らのケア体験を書いた原作の中から、三つのストーリーを選びオムニバス形式の作品にしました。制作のきっかけは、彼らが「世間ではヤングケアラーはかわいそうで、大変そうな幼い子どもというイメージになっている。それだけじゃないことを分かってもらいたい」と言ったことでした。そこから寄付事業に応募して、自己資金と合わせ、制作会社にもご協力いただき、約1年がかりで完成させました。
彼らが原作に書いた言葉をそのままセリフにしていて、高校生たちの葛藤や、打ち明ける勇気、そして一歩踏み出すことで広がる世界を描いています。これまでに各地の自治体や社会福祉協議会などから声をかけていただき、トークショーや講演会とセットで上映しています。
他のケアラーと出会って気づいた「私は私で良い」
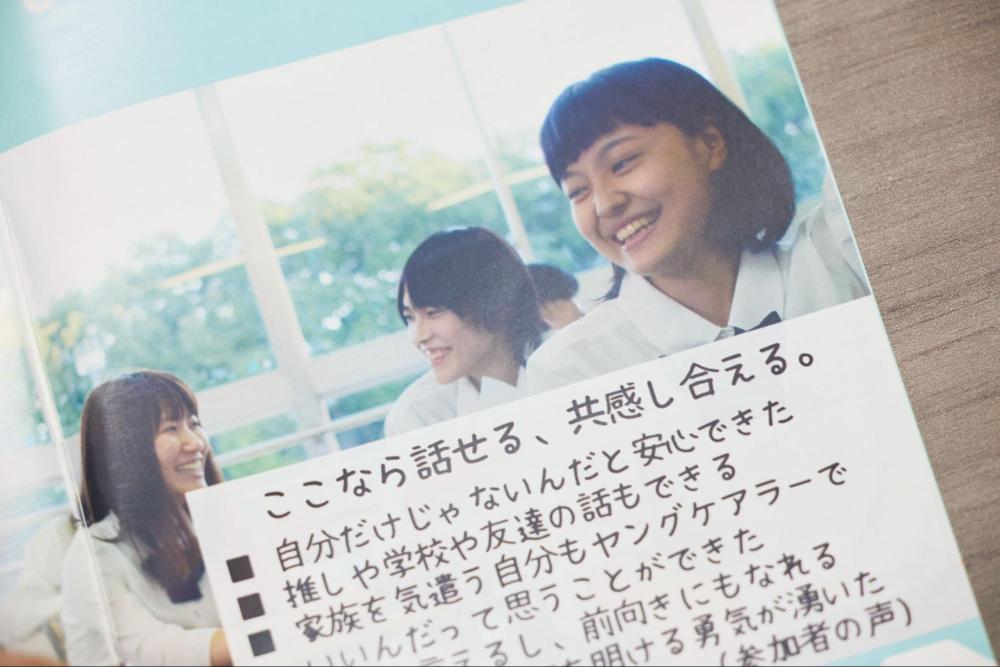
ケアラーアクションネットワーク協会(CAN)のサポートを受けたケアラーからは、交流会に参加したことで、似た境遇の参加者と出会い、前向きな気持ちになれたという声が多く寄せられています。
障害のある兄のケアをする女性は「自分が何者なのか、という悩みがあって、自分に対して肯定できていない感じでした。他のきょうだいさんと話すようになって、(自分は)こういう風に歩んできたんだな、他の人と同じなんだな、私は私で良いんだなっていう風に(思うように)なってきました」。
障害のある妹のケアをする女性は「私は人見知りでうまくしゃべれないところがありますが、人とコミュニケーションをとることが楽しくて、ここ(CAN)では妹のことを隠さなくて良いので、今は普通にしゃべれるようになりました」。
「勇気を出してアクションを起こそう」

私たちは、きょうだいやケアラーには逆境的な経験をプラスに変える潜在能力が備わっていると信じています。そのことに気付いていない人が大勢います。どんな逆境の中にあっても希望を持つことで前に進めるんです。
ただ、希望を叶えるには覚悟と努力が必要です。勇気を出して自ら行動を起こすことが、希望を叶えるアクションになるんです。共にアクション(行動する)を起こしていきたいですね。
そして、きょうだいやケアラーと積極的に出会って希望の光をつないでいってほしいです。それができる場がここ(CAN)です。気軽に交流会に参加してもらえたら、とても嬉しいです。一緒に明るい未来を築いていきましょう。