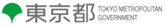コラム&メッセージ

COLUMN 2024.11.21
益田 裕介さん
早稲田メンタルクリニック院長
精神保健指定医、精神科専門医・指導医。防衛医大卒。 防衛医大病院、自衛隊中央病院、自衛隊仙台病院(復職センター兼務)、埼玉県立精神神経医療センター、薫風会山田病院などを経て、 早稲田メンタルクリニックを開業。
YouTubeチャネル「精神科医がこころの病気を解説するCh」を運営し、登録者数は63万人を超える。 患者同士がオンライン上で会話や相談ができるオンライン自助会を主催・運営するほか、精神科領域のYouTuberを集めた勉強会なども行っている。
外来診療を行いながら、診療後に動画を撮影し、YouTubeチャネル「精神科医がこころの病気を解説するCh」を配信している益田裕介さん。
チャンネル登録者数63万人超の人気ユーチューバーでもある益田さんに、こころを軽くする生き方のヒントを伺いました。
《心の病気にならない10の技法》
心が折れそうになったときは、どうすればいいのでしょう。
うつ病にならないためのテクニックを、益田さんが精神科医の目線で解説します。
① 心は脳ということを知る・不調を感じたら休む
不安や孤独を抱えて生きづらさを感じる人は、「自分はメンタルが弱いからクヨクヨしてしまう」と思いがちです。
でも、心は脳が生み出している現象にすぎません。脳が疲れて落ち込んだ状況だから、心が落ち込んでしまうのです。
そういうときは、脳を休ませなければいけません。
脳は疲労がたまるとマイナスな思考を生み出したりするので、不調を感じたらまず休むことが大切です。
② 人間の認知は知識や経験に基づく・知識を増やして世界観そのものを変える
パソコンと同じで、脳がハードウエアだとしたら、心はダウンロードされたソフトウェアといえます。
ソフトウェアは今までの知識や経験です。
知識や経験の不足から、世の中について否定的に思う人もいます。でも、そう思わない人もいます。
自分が思っているのとは違うデータをダウンロードして情報を足すことで、変わることができます。
ネガティブな知識でネガティブに考えていたら、人生はつまらないし、ネガティブに見えてしまう。
自分で知識を増やしていって、世界観そのものを変えて、幸せに生きた方がよいということです。
③ ライフステージを意識する・今の悩みが5年後、10年後も続くことはない

心は脳なので、脳の変化によって10代、20代、30代と価値観が変わっていきます。
特に10代は思春期が始まり、脳が急速に変化している時期です。
脳は30代くらいで完成するといわれていて、20代もまだ違う。
10代で起きていることは20代、30代、40代と続かないし、20代で悩んでいることを30代になっても悩むことはない。
今あなたがとらわれていることは、本当に5年後、10年後も悩んでいるのか、それを意識するだけで大分違います。
あとは世代ごとに解決すべき社会課題が違う。 10代だったら友達、20代だったら恋愛、30代だったら仕事を覚えるとか。
ライフステージを意識して生きると楽だよねということです。
④ 人生の師匠を複数もつ・自分が尊敬する人を心の内側に入れる
「こう生きたらいい」と言われても、人間は理解しにくいものです。
言葉や抽象概念だと、ピンとこないことがありますよね。 メンターが大事です。
自分が尊敬する人を心の内側に入れる、自分の心の中にいる誰か、尊敬できる誰か、そういう人を複数持って、内的な会話をしましょう。
心が安定するためには他者の存在が不可欠で、それがありありとリアリティを持っていることが望ましいです。
⑤ 人生の師匠との心の会話を通じて頭の中を整理する
人生の師匠を複数設定したら、その人と心の中で会話をしましょう。
「こういうときあなたならどうする?」と疑問を投げかけてみると、悩んだりしたときに道に迷いにくくなります。
心の中にいる他者が、自分に対して協力的であることが大事で、彼らとの会話を通じて頭の中を整理していく、自分の問題や課題を整理することができます。
⑥ 自他の境界を引く・自分と他人は違うことを意識する
泣いたら母乳をもらえる赤ちゃんは、お母さんと自分の区別がついていないと言われています。
時間が経つにつれて、自分とは別の人間で、違う人生を歩んでいることが分かってきます。
同じようにして、友達も、自分とは違う価値観で、好きなものが違うのだなということが段々分かってくるのです。
でもやっぱり、違うと思っても、違うと思い切れないのが人間なので、悩んだときに、違う人間なのだなと理解しておくと、心が楽になるということですね。
⑦ 自分の中の妬みに気付く・強い感情に気付くことでストレスを感じにくくなる
妬みというのは、とても危険で強い感情です。
危険な感情には自分自身が気付きたくないし、他人にも気付かれたくありません。
このため、「あの人がうらやましい」と思っていても、それを妬みとは気付かず、「あの人と違って自分がこうなのは、自分が悪いからだ」と、頭の中で無意識に変換してしまいます。
自分の妬みに気付くと、自分を責めることも少なくなり、ストレスを感じにくくなります。
⑧ 無意識を理解する
人間の心というのは、自分で意識していないことがたくさんあります。
にもかかわらず、全部自分でコントロールできているかのように思っています。
周りもそう思っているから、自分をコントロールできない人は「甘えている」などと見られてしまいがちです。
でも甘えているのではなくて、無意識に動いていることもある。
自分もそうだし、相手もそういうことがあると理解すると見え方が変わってきます。
⑨ 自分の弱さを認めてあるがままの自分や他者を愛する
精神科の治療のゴールは何かというと、ひとつは「仕方がない」と思えることです。
自分の弱さを責めるよりも、「仕方がない」と受け入れて愛してあげた方が、不安やトラウマに支配されず、心はずっと軽くなります。
やらないのではなく、できないのです。
だからそれを責めるよりは愛してあげた方がいいよという話ですね。
他者の感情を受け流す力を高める、自分の弱さを認めて、あるがままを受け容れる、やれることを淡々とやる、ということです。
⑩ 日々マインドフルネスをする・座禅ないし冥想をして心を整える

心は脳であり、学習によって成長し、変化していきます。
その成長に一番大事なものが、規則正しい生活であり、自分自身と向き合う時間です。
日々、座禅ないし冥想をし、目を閉じて呼吸を意識した所作をすることが重要です。
マインドフルネスをする中で、心を整えることができます。
不安なときは、頭が活性化していて、心臓も速く呼吸も浅い。呼吸をゆっくりすることで、身体に引っ張られて、頭の中もリラックスします。
呼吸に戻る、ゆっくりする、落ち着く、自分を見つめることで、そこにある価値観、カルチャーに興味を持つと思います。
それが、あるがままを認める、真実を受け容れる、生まれてきてよかったと思う、解決できないものを受容していくということです。
《ついやってしまいがちな4つの心の動き》
相手に誤解されたと思ったり、相手が妙にイライラしていると感じて不安になってしまったりすることはありませんか。
知っておくと心が軽くなる、人間がついやってしまいがちな4つの心の動きについて、益田さんが解説します。
① 投影
投影とは、自分の感情に気付かずに、相手がその感情を持っていると感じてしまうことです。
例えば、自分がイライラしていることに気付かず、「相手がイライラしている」と感じてしまうのです。
投影が起こると、「自分は怒っていないのに、相手は何で怒っているのだろう」などと誤解や不安が生じます。
② 転移
転移とは、過去の記憶に由来するもので、過去に嫌なことがあったときに、自分で気付かないうちに、相手にその像を重ねてしまうことです。
例えば、「昔、意地悪をされた人に似ている」と思ってしまうと、相手をよく理解していないのにも関わらず、
無意識に「意地悪な人」と思ってしまうのです。
③ 投影同一視
投影同一視とは、自分が怒っているときに、相手を怒りの象徴だと考えることです。
自分の不安や感情のメタファーを現実に作ってしまう。
例えば、自分が劣等感を感じているときに、
嫉妬の対象を作って、その人をいじめたり攻撃したりすることで解消しようとします。
自分が持っていないのが悔しくて、持っている人をいじめることで自分の不安を解消しようとする。
10代や20代は投影同一視が起こりやすいので、これを知っていれば、いじめの対象にされたときに自分が悪いのかなと思わずに済むことも多いです。
④ 逆転移
逆転移とは、相手の感情を無意識に察知して、自分の感情だと勘違いしてしまうことです。
例えば、相手がイライラしていたり、相手から怒りの感情をぶつけられたりしたときなど、
自分も相手に対して怒りの感情を抱いてしまいます。
《生きづらさを解消するためのQ&A》
不安や孤独を感じたときや、誰にも相談できないときはどうすればいいのかなど、気になる疑問に益田さんが回答します。
Q. うつっぽいと感じたときはどうすればいい?
A. うつっぽいと感じたら、まずは冥想してみましょう。
これを5分以上できるかできないかが、ひとつのポイントになります。
あくまで目安ですが、5分以上できない場合は、大分調子が悪く、ゆっくり休むことが大切です。
その上で誰かに助けを求め、相手の指示に従います。
5分以上できる人は自分と向き合い、情報収集する。
そうすると大体、うつになった原因というのはストレス、疲れがたまっているからで、疲れがたまっているのは何故かというと、人間関係、仕事、勉強など、問題が出てきます。
どんな問題があるから、うつっぽくなっているのか、まず問題を整理してみる。
その上で問題を1個1個泥臭く解決していく。問題によってはスケジュールを見直した方がいいということですね。
Q. うつっぽいときに逆にしない方がいいことは?
A. 大きな決断をする、大きな買い物をする、宣言するなど、自分の行動を変えるようなことはよくないですね。 やめた方がいいです。
自分を責めるのもよくないけど、仕方がないんですね。
だから、仕方がないなと思いながら周りの人に助けてもらう。
Q. 周りに助けを求めにくい場合は?
A. 周りに頼れる人がいない、あるいは相談しにくい、誰に相談したらよいか分からないという場合は、プロに相談するのがいいと思います。
福祉なり医療なり、その道の専門家や相談窓口などに助けを求めてみてください。
プロに相談した上で、自分の周りの誰を頼ればいいのか、助言をもらうのもひとつの方法です。
Q. 不安な気持ちを断ち切るにはどうすればいい?
A. まず深く深呼吸をしましょう。
不安なときというのは、不安な感情に脳が支配されて、心臓の動きも早く、呼吸も浅くなっていることが多いものです。
呼吸をゆっくりしてあげると、心臓の動きがゆっくりになり、脳もリラックスします。
強制的に脳をリラックスさせてから、不安の原因は何なのかを考えてみましょう。
《不安や悩みのある方へ》

10代・20代というのは、不安を感じる時期で、脳の成長過程から、そういうものです。
それは、運動するとお腹が空く、夜になると眠くなるのと同じようなもの。
だからこそ、その時期に脳が成長し発達するので、いろんなことを考えながら、自分はダメだと思わずに、成長していく楽しみみたいに思えるのがよいです。
繊細な時期も、1つの過程だと思って。
そういう時期が、人生の中で一番幸せだったりもするしね。
精神科の治療は、「仕方がない」と思えることがゴールのひとつです。仕方がないと思って、不安やトラウマに支配されず、建設的な行動をとること。
ただそれだけ、それでしかないのです。
あとは、「生まれてきてよかった」と思える瞬間を少しでも増やすことです。
人生は常に問題があって、ここにいったら幸せになるとか天国になるとかそういうものじゃない。
治療イメージ、ゴールのイメージができると逆算的にいろんな問題が解決できるようになると思います。