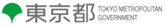サポート紹介&利用者の声

SUPPORT 2025.07.22
~人はもっとやさしくて!社会はもっとおもしろい!! ~
特定非営利活動法人 文化学習協同ネットワーク
特定非営利活動法人 文化学習協同ネットワーク 代表理事 佐藤 洋作さん/コミュニティベーカリー 「風のすみか」研修責任者 廣瀬 日美子さん
文化学習協同ネットワークとは?

勉強の苦手な子どもたちの保護者から「子どもに勉強を教えてほしい」と言われて、アパートの一室で学習支援を始めたのが1974年のことでした。それから半世紀以上、子どもたちに、自宅でもない、学校でもない、第三の居場所(サードスペース)を提供し続けてきました。
1993年にフリースペース「コスモ」を開設して不登校児童の居場所づくりを本格的にスタート。1999年には子ども・若者支援全般に取り組むNPOになり、地域や自治体とも連携しながら、子どもと若者の居場所づくり、学習サポート、就労支援などさまざまなプログラムを提供しています。
特徴的な事業としては、「風のすみか研修プログラム」があります。コミュニティベーカリー「風のすみか」での就労体験が柱になっていて、若者たちが「社会」とつながる場でありたいと考えています。
若者に自信を持ってもらう就労体験

文化学習協同ネットワーク全体では現在、約1,000人程度の若者の就労を支援しています。ただ、その出口はとても狭いと感じます。支援を必要としている若者たちは他人と競争しながら働くことに恐怖感を持っていたり、自分に自信を持てなかったり、ひとりひとりに様々な事情があります。
そんな若者たちに、私たちが自信をもって紹介できる事業所がどれくらいあるのだろう、と考えるうちに、自分たちの元で就労を体験してもらう場を提供したい、と考えるようになりました。
ただ働けというだけでは、自信を持てない若者たちを追い込んでしまいますから、働くことは怖いことではなく、楽しいことだと感じてもらえる場にしたい、と思いました。そのひとつが2004年にオープンしたコミュニティベーカリー「風のすみか」です。
(写真右は佐藤洋作さん、左は廣瀬 日美子さん)
コミュニティベーカリー「風のすみか」の誕生

なぜベーカリーだったかというと、働く体験の基本のひとつが「ものをつくる」仕事だと思ったからです。そして調べていくうちに、ある福祉支援団体が、障害者雇用の場としてパン屋さんを運営・支援をしていることを聞いて、我々も若者の就労支援の場としてパン屋さんをやってみようと考えました。
ただ、就労支援をするわけですから、仕事を体験する若者たちに教えられなくてはいけないんですよね。当時私たちのスタッフにはパンを焼くことができる人は皆無でした。だから本当に困りました。
不登校支援のスタッフの中にひとり、趣味がパンづくりというメンバーがいたので、担当に入ってもらうことにしました。さらに人手が必要なので、団体を支援してくれている保護者の皆さんにも協力してもらいました。
また、パン作りをする場所がなかったので、当初は近隣の公民館を借りてみんなでパンをひたすら焼きました。素人ばかりなので、最初はまったくうまく焼けません。売りものにならないので、支援者や保護者の皆さんにパンを食べてもらい、感想をもらって改良や工夫を重ねました。協力を申し出てくれたベーカリーがあり、そこのパン職人さんを派遣してもらって助言を頂きました。そんな試行錯誤を約1年間続け、コミュニティベーカリー「風のすみか」をオープンしたのが2004年のことでした。
ベーカリーの軌跡、若者へのメッセージに

店はオープンしましたが、宣伝費用もなかったので、地域の方の支えと口コミが頼りです。近くの学校でチラシを配らせてもらったり、新聞や地元のケーブルテレビに取り上げてもらったりして、皆さんの協力によって徐々に地域で認知されていきました。
パンはすべて、国産小麦にこだわった天然酵母で焼き上げています。天然酵母は天候に左右されるので、準備がとても大変です。天気予報を見ながら仕込むんですけど、午前中で売り切れてしまったり、逆につくりすぎてしまったり。最近は、原材料費の高騰も頭の痛い問題です。
手を差し伸べてくれたベーカリーや、保護者・地域の皆さん、店を取り上げてくれたマスコミ、どのサポートが欠けてもうまくいかなかったと思うんですね。「風のすみか」の軌跡が、がんばり次第で未来を開いていけるというメッセージとして若者に届けばいいな、と思うんです。
就労体験を通じてつながる自分と社会

コミュニティベーカリー「風のすみか」での就労体験プログラムは、約4カ月間仲間と一緒に成長を目指す内容です。現在は若者5人ほどが参加しています。サポートするスタッフも団体のプログラムを巣立ったメンバーが中心です。
まずはパンをつくる準備や片付けなど基本的なことからスタートして、慣れてきたらパンの製造や店頭での接客、出張販売イベントの配達など、様々な仕事を体験してもらいます。うまくいったことを中心に、毎日振り返りの時間を設けています。
若者たちには、失敗を恐れて一歩が踏み出せなかったり、人間関係が原因で仕事から遠ざかっていたり、様々な事情があります。ひとりひとりにあわせてスタッフがサポートしたり、仲間同士で励まし合ったりしていく中で、自分ができることや仕事の楽しさに気づき、自分と社会のつながりを見いだしていきます。
お店に来た人に喜んでもらえる、「おいしかった」と声をかけてもらえる、リピーターになってもらえる、こういう体験をすると、仕事を続けたくなりますよね。
広がる活動の場
2023年 には、三鷹駅近くのシェアキッチンで手作りのカフェ「すみかふぇ」(毎週水曜日営業)をオープンしました。「風のすみか」で育った若者が中心になって立ち上げた店で、「風のすみか」で焼き上げたパンを使ったバインミーやハンバーガーなどを提供しています。メニューも自分たちで考えて、季節にあわせた商品を提供しています。
ベーカリーやカフェで提供する食材は、ニローネ「風のすみか」農場(神奈川県相模原市)で栽培したものを中心に使用しています。こちらでは農業を中心とした就労研修プログラムを提供しています。
サポートを担うスタッフはどんな方々ですか

たとえば、風のすみか研修プログラムを受ける若者ひとりに対して、若者サポートステーションのスタッフと連携しながらふたりひと組でサポートする体制を組んでいます。
我々のスタッフには様々な背景のメンバーがいます。社会福祉士や教員免許などの有資格者、あるいは団体がサポートしたメンバーなど、本当に様々です。スタッフ同士で大事にしていることは、日々の悩みや子どもとの接し方など様々なことをスタッフの間で共有しながら一緒に成長していく姿勢です。
スタッフとして活動してみたいという方がいれば、まずはやってみてもらうことにしています。もちろん、やってみてうまくいかないこともありますが、文化学習協同ネットワークでサポートに加わった体験が、次の仕事先へのキャリアとして通用する団体でありたいと願っています。
活動のベースは「居場所」

私たちの活動のベースは「居場所」です。人と人が出会って、他者との対話を通して自分の存在を自分で認められるようになる、そういう場です。そして外の社会に目を向けたときに仕事の世界がある。始めから仕事=就労支援ではないんですね。
仲間と一緒に活動するうちに、自分の持ち味が見えてくる。「自分はダメなんだ」と落ち込んでいた若者が、自分だけじゃないということに気づいていくわけです。
支援したひとりに、人の気持ちを理解することが苦手な若者がいました。でも、本人はそのことに気づいていないわけです。誰が気づかせてくれるかというと、仲間たちが気づかせてくれるんですね。仲間から指摘を受けるんですけど、本人は変わりません。だけど、そのことに気づくことで、いわば取説(取扱説明書)ができるんです。自分が変われないのなら、関係性を変えれば良いんです。人との関係性の中から社会(仕事)へとつながっていくわけです。
私たちは長年、個人の生きる体験を居場所を通してサポートしてきました。働く場、相談の場、などいろんな選択肢を示せることが強みだと思っています。
団体の利用者の声

風のすみかの就労体験プログラムに参加した卒業生のコメントを紹介します。
20代の女性は「お客様や一緒に働いている人の笑顔が見えたときや、ありがとうと言われた時、できることが増えて自分の成長を感じた時や思いがけない出会いがあった時はやっぱりうれしかった」と、述べています。
また、現在は販売員として働く20代の男性は「研修中は、たくさんの失敗をさせてもらいました。その経験から、仕事で失敗しても自分なりに整理して対処することができるようになりました」と、コメントを寄せています。
この記事を読んでいる方へ

ひきこもりや不登校は医療的なケアで治るというものではありません。私たちは皆さんにちょっと手伝ってもらえるような、そんなプログラムをたくさん用意しています。
保護者の方からの相談も歓迎です。本人が外に出ることが難しい場合は、まず保護者や周りの方が面談に来て下さい。引きこもっている本人もこのままで良いとは思っていないけれど、急に変わることは難しいでしょう。だから選択肢を提示してあげて、機が熟すのを待つことが大切です。
きっかけがあれば外に出られるようになることも多いんです。彼らが自尊心を傷つけずに外へ出られるタイミングを一緒に待ってみましょう。