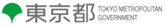サポート紹介&利用者の声

SUPPORT 2025.10.29
~ひとりにしない、つながりが生まれるきっかけに~
NPO法人ピアサポートネットしぶや
ピアサポートとは、「仲間・対等」という意味のpeer(ピア)と、「支え合い」を表すサポートを組み合わせた言葉で、同じような立場や経験を持つ者同士が支え合うことを意味します。
関わっていくうちに、もちろん教えることもあるけれど、子どもたちからも様々なことを教わり、お互いに成長していくことがピアサポートの趣旨なのです。
生きづらさを感じている方はもちろん、ひきこもりのお子さんの両親(家族)の方からの相談もお待ちしています。
NPO法人ピアサポートネットしぶや 理事長 相川 良子さん/統括リーダー 石川隆博さん
ピアサポートネットしぶやとは?

ピアサポートとは、「仲間・対等」という意味のpeer(ピア)と、「支え合い」を表すサポートを組み合わせた言葉で、同じような立場や経験を持つ者同士が支え合うことを意味します。当団体ではお互いを支え合い、育ちあうことをコンセプトに活動しています。
1990年代に、社会の変化によって人間関係が希薄化する中で、子どもたちが社会や地域となじめるよう、中高生対象の居場所づくりを始めたのが団体のスタートです。以降、学校と地域の間に子どもたちが立ち寄れる居場所の提供を中心に、様々なサポートを提供しています。
社会教育事業から地域の活動へ
1998年度に、渋谷区の上原社会教育館 主催の中高生倶楽部 が立ち上がりました。これは、子どもたちに放課後の居場所と、様々な活動をのびのびとできる場を提供する事業で、近隣の中学生を中心に多くの子どもたちが集まりました。特に人気だったのが、当時若年層の間で流行っていたバンド活動です。子どもたちもロックバンドに夢中になり、活動は非常に盛り上がりました。
この活動は翌年度から、PTAや地域の人たちを主体とする地域団体「上原ファンイン」に引き継がれ、現在も続いています。ファンインには中国語で「歓迎」という意味がありますが、「ン」(運)が二つ付くということで縁起が良いという意味も込められています。
その後、活動を渋谷区全域に広げるための呼びかけも行いました。各中学校区で中高生の居場所づくり活動が始まり、「渋谷子どもの居場所づくり実行委員会(渋谷ファンイン)」が誕生します。2004年には、不登校など多様な課題に積極的に取り組む「渋谷ファンイン・ピアサポート委員会」を設立。2009年に法人化して「ピアサポートネットしぶや」となり、それまで小中学生に限っていた支援対象を、概ね15~34歳までの若者へと広げ、現在では中高年を含む全年齢へのサポートを提供しています。
居場所づくりを起点に寄り添い、伴走する

現在は、居場所づくりを起点に、ひきこもりなど生きづらさを感じる子どもや若者、およびその家族をサポートする活動をしています。
フリースペース は月曜を除く10時~16時に開放していて、自由に過ごすことが出来る場所です。パソコンやマンガが置いてあるほか、好きなものを持ち込んで楽しむことも可能です。近隣の大学生を中心としたボランティアやピアサポーター(支援員)を配置しているので、勉強を教わったり、趣味や興味のある話題を話したり、することもできます。
また、渋谷区内では四つの中学校で放課後の居場所支援活動を実施しています。このうち2校では学習支援(各週1回)、残りの2校ではカフェ(各月1回、軽食と飲み物を提供)を行っています。部活動や習い事までの時間を過ごせる場になっています。
支援対象の中高生は、思春期にあたる多感な時期で、人間的にも大きく成長する時でもあります。そうした人生の変わり目にいろんな人と関わる機会をつくることが狙いです。
(写真はピアサポートネットしぶや提供)
担い手はピアサポーターやボランティア

ピアサポーターは、子ども・若者と対等な存在として1対1(マンツーマン)でかかわりを持って伴走していきます。
団体では育成プログラムを用意していて、社会福祉や人権などに関する研修や事例研究、実習を通じてスキルアップを図っています。
また、近隣の大学生など約50人がボランティア登録していて、主に子どもたちの学習支援や見守りなどに携わっています。
ただ、人との関係づくりは研修を受ければうまくいくというものではありません。最初のうちは、子どもたちに無視されてしまってどうしたらいいかわからない、ということもよくあります。
無視というより、最初はお互いに全くの他人なわけですから、当然警戒します。それでもどうしたらいいのかを必死に考え、何度も話題やタイミングを変えてしかけ、失敗を繰り返しながら少しずつ相手の心に入り込んでいく。人との関係づくりはそういうものだと思います。
そうして関わっていくうちに、もちろん教えることもあるけれど、子どもたちからも様々なことを教わり、お互いに成長していくことがピアサポートの趣旨なのです。
(写真はピアサポートネットしぶや提供)
子ども・若者に伴走する自立応援プログラム
団体の特徴でもある「自立応援プログラム」は、不登校やひきこもりの子どもとその家族を対象にしたサポートです。訪問相談を行っており、保護者や学校をタテ関係、同級生などとのヨコの関係とすると、そうではないナナメの関係 で伴走することを目指しています。
たとえば親との関係が良好でないケースでは、お父さんとは会話を全くできないけど、お母さんとは会話はできるという場合があります。そういう時は、お母さんを中心に関係を築きながら、親子間でも信頼関係を深めてもらい、少しずつお子さんにアプローチを図っています。
また、一人で外出することが難しいお子さんの外出同行といった支援も行っています。
ひきこもる前から関わりを持つ

ひきこもり相談に来るのは、20代前半のひきこもりのお子さんがいる保護者 の方が非常に多いです。話を聞くと、我々に相談に来る前に一度はどこかに相談しているケースが多いです。医療機関だったり行政の窓口だったり、相談先は様々ですが、その時に何らかの違和感を感じてしまい、相談が続かずにそれから5年以上が経ってしまったというケースがたくさんあります。
そして、長い期間を経て保護者の方から連絡を頂くわけですが、その子(若者)が5~7年くらい前というと、だいたい小学校高学年から中高校生くらいにあたります。成長する中で周りの人との関わりが欠かせない時期なのに、学校に行くことができず、人との関わりがつくれないというのはもったいないことです。
また長くひきこもっている方の場合、本人が再び外部の人との関わりを持ったり、社会になじめるようになったりするまでには相当の時間がかかることが多いです。
行政や他団体とのつながりも模索
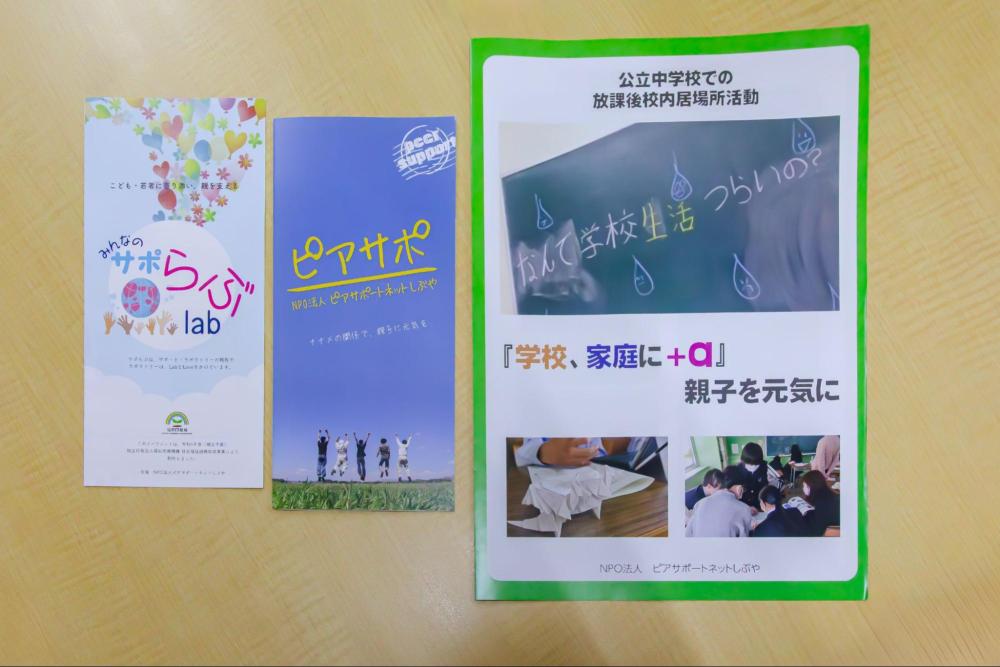
ですから、学齢期から多くの人とつながりを持って、困ったことがあったら早目にサポートを受けられるという体制をつくることが大切だと考えています。
子どもの幼少期には福祉の窓口が子どものサポートを担うことが多いわけですが、学齢期になると、福祉行政から学校へと、子ども支援の中心が移ります。ただ、病気になるとまた福祉に移ります。支援を担う主体が変わると、情報がうまく引き継がれなかったり、地域との関わりが希薄になって情報が届かなくなったりすることがよくあります。この点は大きな課題だと感じています。
そこで、地域の中に、幼少期から子ども食堂や遊び場があって、いつでも支援を受けられる状態をつくりたいと思っています。たとえば渋谷区の場合は社会福祉協議会が中心となって、地域福祉コーディネーターさんが地域共生社会の実現を目指して活動しているので、そういった方と連携しながら行政を含めたネットワークをつくる努力をしているところです。
団体とのつながりが原動力に
団体のサポートを受けて社会に出て、現在は飲食関係の仕事をしている男性 は「ピアサポートネットしぶやの支援のお陰で、ひきこもりだった自分が人との関わりを持ち、やがて社会に出て働けるようになりました。ただ、これまでつながった方々との関わりを持ち続けたくて、今でも団体のメンバーとして登録しています。いつでも相談できる、その思いが自分にとってお守り代わりになっていて、仕事を頑張る原動力になっています」。
とにかく相談を

私たちピアサポートネットしぶやは、相談に来られた方をこちらから拒むことは決してありません。生きづらさを感じている方はもちろん、ひきこもりのお子さんの両親(家族)の方からの相談もお待ちしています。
ご相談は、可能であれば対面でじっくりお話をうかがうようにしていますが、まずは電話(03-6459-3848)か、メール(info@peersupport.jp)で構いません。どんなささいなことでも構いませんので、いつでもご相談ください。